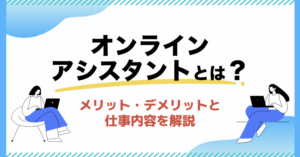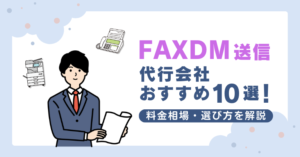個人事業主と社長の違いは?肩書きに迷ったらこの記事で解決
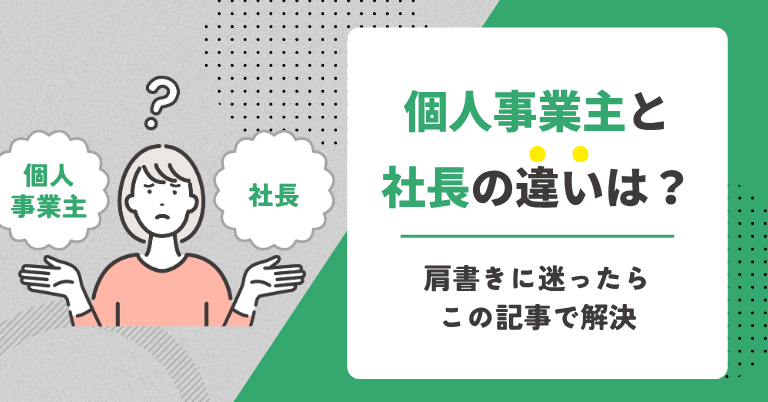
個人事業主として事業を進めていると、「社長」と名乗っていいのか肩書きに迷う人もいます。事業のトップという意味ではどちらも同じですが、明確な違いがあるため、しっかりと理解しておきましょう。
本記事では、下記をまとめました。
- 個人事業主と社長の違い
- 個人事業主と社長の肩書きの使い分け方
- 個人事業主と社長の税金や手続きの違い
自分の事業にとって最適な形態を選びたい方は、ぜひ最後までお読みください。
「社長」と名乗れるほど事業が大きくなると、自分ひとりではリソースが足りなくなります。従業員を雇うのもひとつの方法ですが、業務にあわせて柔軟に対応できるオンライン秘書の活用がおすすめです。
オンライン秘書・オンラインアシスタントサービス『i-STAFF』は、経理や営業サポートなど幅広い業務を代行します。依頼者は自身のコア業務に専念できるため、さらなる利益向上を目指せます。
i-STAFFの詳細は、下記よりご確認ください。
目次
個人事業主と社長の違い

個人事業主と社長には、下記の違いがあります。
- 開業の方法
- 法律上の立場
- 会社の規模や組織
- 社会的な見え方
特に、個人事業主と社長では、社会的な信用度合いが異なります。一般的に、社長のほうが社会的信用度が高いため、「社長」と名乗りたい人もいるでしょう。ひとつずつ具体的な内容を解説します。
開業の方法
個人事業主と社長では、そもそも開業方法が異なります。
個人事業主の手続きはシンプルで、管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出するだけです。手続きに費用はかかりません。
一方、社長になるためには、まず「会社(法人)」を設立する法的な手続きが必要です。個人事業主の開業と比べて複雑で、費用も時間もかかります。
たとえば、株式会社を設立する場合、会社のルールである「定款」を作成しなければなりません。認証を受け、法務局へ「設立登記」の申請を行います。自分ですべて行っても、登録免許税や認証手数料などの費用が必要です。
法律上の立場
個人事業主は、法律上「事業と個人が一体」となる「自然人」として扱われます。そのため、事業で負債が発生した場合は、事業用のお金だけでなく私的財産を使って返済しなければなりません。
社長は、法律上「会社と社長は別人格」とされ、法人格の代表者として扱われます。会社の負債はあくまで会社の財産で返済するもので、社長が負う責任は原則として「自分が出資した金額の範囲内」に限定されます。
このように法律上の立場について大きな違いがあります。
会社の規模や組織
個人事業主は、法的な組織という概念はなく、すべての意思決定と責任が個人にあります。また、小規模な場合がほとんどです。
一方、社長は、法律に基づいた組織構造が求められます。個人事業主と比べて、規模が大きいです。
たとえば、株式会社では株主と経営者が存在します。役員には任期があり、任期が終わるたびに登記手続きが必要です。
このような組織構造が、事業を大きくします。法人は、株式の発行によって他人から出資を受けたり、取締役の任命で権限を委譲したりすることを前提に設計されているのです。
社会的な見え方
一般的に、社長は個人事業主と比べて、高い社会的信用力を持ちます。なぜなら、法人は法務局での設立登記によって、存在が公に証明されているからです。この透明性が信用のもととなります。
また、銀行から融資を受けるためには、厳格な審査を通過しなくてはなりません。つまり、融資を受けている事実が信用の証になるのです。
一方で、個人事業主の信用度は社長と比べて低い傾向にあり、取引企業によってはリスク管理上、個人事業主との取引に制限をしている場合があります。
このように、会社の社長であることが信用度を担保するケースがあるのです。
個人事業主と社長の肩書きの使い分け方

個人事業主と社長の肩書きの使い分けについて、下記の点から見ていきましょう。
- 「社長」という肩書きに法的な根拠はない
- 個人事業主が「社長」と名乗っても問題ないが誤解を招く可能性がある
- 個人事業主におすすめの肩書き
「社長」という肩書きには「個人事業主」にはないメリットがありますが、法的な位置づけは意外と曖昧です。「自分がどう名乗りたいか」ではなく、「相手にどう伝わるか」で選びましょう。順番に解説します。
「社長」という肩書きに法的な根拠はない
「社長」という肩書きは、法律で定められた役職名ではありません。あくまで、組織の最高責任者であることを示すための、呼び方のひとつに過ぎないのです。法的な根拠のある正式な肩書きは「代表取締役」です。
つまり、一般的に「社長」という肩書きは威厳や信用を持ちますが、法的な証明にはなりません。自分自身の肩書きについて悩んでいる場合は、この点をしっかりと把握しておきましょう。
個人事業主が「社長」と名乗っても問題ないが誤解を招く可能性がある
「社長」は法律で定められた肩書きではないため、個人事業主が名刺やWebサイトで「社長」と名乗っても、法律で罰せられることはありません。しかし、法的に問題がなくても、ビジネスにおいて問題がないとは言い切れません。
一般的に、「社長」という肩書きは「会社の代表者」をイメージさせます。個人事業主がこの肩書きを使うと、取引相手に「この人は法人の代表なのだろう」と誤解を与える可能性があります。
もし相手が「法人であること」を取引の判断基準にしていた場合、あとで個人事業主だと分かると、信頼関係に影響を及ぼすリスクがあります。
また、「代表取締役」や「取締役」という肩書きは法的に使用できないので注意しましょう。
個人事業主におすすめの肩書き
個人事業主が「社長」という肩書きを使うのは好ましくないので、どのような肩書きを使えばいいのかおすすめを紹介します。基本的には、相手に不要な誤解を与えず、自分自身の価値を的確に伝えるものを選ぶべきです。
おすすめなのは「代表」「代表者」です。最も一般的で無難な肩書きで、事業の代表者であるという事実を誇張なく伝えられます。
「Webデザイナー」「ビジネスコンサルタント」など、具体的な職種名をそのまま肩書きにするのもおすすめです。相手に「何を提供できる人なのか」が伝わるため、ビジネスチャンスの創出につながります。
個人事業主と社長の税金や手続きの違い

個人事業主と社長は、定義や社会的信用度以外にも税金や手続きにも違いが見られます。ここでは、下記の4つについて解説します。
- 税金の計算方法
- 経費にできる範囲
- 確定申告の内容
- 社会保険の扱い
個人事業主から社長になることを検討するうえで、最も重要なのが「お金」に関することです。特に、税金と社会保険の仕組みの違いは、収益に直結します。順番に見ていきましょう。
税金の計算方法
事業で得た利益に税金がかかるのは共通ですが、個人事業主と社長では仕組みが異なります。
個人事業主は、利益に対して「所得税」が課されます。累進課税という仕組みが適用され、所得が増えれば増えるほど税率も段階的に上がるシステムです(5%〜45%)。
一方で、社長の場合は会社の利益に対して「法人税」、社長個人に支払われる給与に対して「所得税」が課されます。
このように「社長」が支払う税金は、利益が会社と個人に分散されるのです。普通法人の法人税率は、所得における年800万円以下の部分は15%と、個人事業主の最高税率(45%)に比べて低く設定されています。
そのため、個人事業主としての所得が600万〜800万円を超えてくると、高い所得税を払うよりも法人化して法人税と給与にかかる所得税を組み合わせて支払うほうが、トータルの税負担が低くなる可能性が出てきます。
経費にできる範囲
個人事業主と社長では、経費にできる範囲が異なります。社長のほうが、経費にできる項目が多いです。代表的な項目は、下記のとおりです。
- 社長の給与(役員報酬)
- 退職金
- 社長の生命保険料
個人事業主は、本人への給与や退職金を経費にできません。また、自宅で仕事をする場合、家賃や水道光熱費などは事業で使った割合だけを家事按分として経費にできます。ただし、その割合の根拠は税務調査で厳しく問われることも多いです。
確定申告の内容
税金の申告手続きも大きく異なります。個人事業主は、確定申告を行う必要があります。確定申告には青色申告と白色申告があり、高い節税効果を得るためには複雑な青色申告を行うのが一般的です。しかし、青色申告であっても法人の税申告と比べればシンプルで、申告先も原則として税務署のみです。
一方、社長の申告手続きは、個人事業主と比べて複雑になります。申告書の作成は専門知識が必須なため、税理士への依頼が一般的です。
また、法人の場合、事業が赤字であっても納税義務が発生します。たとえば、事業が赤字になっても法人住民税は全額免除にはならず、最低でも7万円を支払わなくてはなりません。
社会保険の扱い
個人事業主は、原則として「国民健康保険」と「国民年金」に加入し、社会保険には加入しません。しかし、「常時雇用する従業員が5人以上」の場合、業種によっては社会保険に加入する必要があります。
一方で、法人から給与を受け取っている社長は、従業員数が自分1人であっても「健康保険」と「厚生年金」への加入が法律で義務付けられています。
保険料は社長の給与額に基づいて計算され、その金額を会社と社長個人が折半し、半分ずつ負担します。
個人事業主から社長になるとどう変わる?

個人事業主から社長になると、下記の変化が見られます。
- 社会的信用が高くなる
- 経費や節税の幅が広がる
- 事業を大きくしやすくなる
- 設立や維持の手間とコストがかかるようになる
税金や社会的な立場で「社長」にメリットはありますが、設立の維持や手間がかかります。ひとつずつ見ていきましょう。
社会的信用が高くなる
個人事業主から社長になると、社会的信用度が高まります。設立登記によって公的に存在が証明され、法務・税務のルールに従うことで、金融機関からの資金調達につながります。
結果として事業の安定性を示せるため、大手企業との取引や優秀な人材の確保がしやすくなるのです。社会的信用の向上は、事業を拡大・発展させるための基盤構築につながります。
経費や節税の幅が広がる
個人事業主と社長では、経費にできる項目や税金の仕組みが異なるため、節税の効果が大きくなります。
たとえば、給与(役員報酬)を経費にできます。業務実態によっては家族を役員にして役員報酬を支払うことで、世帯全体でかかる所得税の総額を軽減できる可能性があります。
また、個人事業主が支払う所得税と会社が支払う法人税では税率が異なり、社長が支払う税額を抑えられる可能性があります。
事業を大きくしやすくなる
法人化することで個人事業主は社長になりますが、事業は「個人」から「組織」へと変化します。
組織となった事業は、個人事業主にはない「株式の発行」により、外部から出資を得られます。結果として、資金調達がしやすくなり、新たなチャレンジが可能です。
また、事業承継もスムーズです。法人は社長が変わっても、登記を変更すれば会社(法人格・資産・口座)はそのまま存続します。
設立や維持の手間とコストがかかるようになる
社会的信用や節税効果、事業拡大などのメリットがある一方で、会社を設立・維持する手間やコストが発生します。
たとえば、会社設立のコストはもちろん、社会保険料の加入とその会社負担分の維持コストが発生します。さらに、専門知識を要する税務申告においては、専門家に依頼する費用も必要です。
また、個人事業主時代には存在しなかった社会保険の手続きや役員変更登記、株主総会の運営など、本業以外の事務作業も増加します。
事業拡大の際は秘書の導入を検討しよう

個人事業主から社長になると社会的信用や資金面で有利となり、事業の拡大につながります。しかし、税務申告や社会保険手続きなどの管理業務が増加するため、1人で事業運営を続けるのは困難です。
従業員を雇うことで解決に近づきますが、採用コストや教育コストを負担しなければなりません。そこで、おすすめなのがオンライン秘書の活用です。
オンライン秘書とは、必要な業務を必要な時間だけ、高い専門性を持つ外部のスタッフに業務を委託できるサービスです。
その対応範囲は、スケジュール調整といった秘書業務に留まりません。法人化によってまさに必要となる「経理・財務」、「人事・労務」、「Web・SNS運用」など、バックオフィス業務全般をカバーします。
オンライン秘書・オンラインアシスタントサービス『i-STAFF』は秘書業務はもちろん、「振込代行」「記帳代行」「見積書・請求書作成」「給与計算サポート」などの経理・労務の専門業務に対応できる高いスキルを持っています。
さらに、返金保証制度を導入しているため、初めて利用する場合でも安心です。事業拡大をお考えの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
1人社長がアウトソーシングを活用すべき理由やポイントを解説しているので、こちらの記事もぜひご覧ください。
1人社長こそ業務委託をうまく活用しよう!依頼方法・外注化のポイントを解説
また、i-STAFFの評判や口コミをまとめた記事もあります。あわせてご覧ください。
オンラインで業務を
アウトソースするならi-Staff
こんな事でお困りでは御座いませんか?
・スタッフの雇用コストが高い・・
・雑務に追われてコア業務に集中が出来ない・・
・とにかく今すぐ業務を手伝って欲しい!
こんなお悩みがあれば、i-Staffで解決できるかも知れません!
【i-Staffが選ばれてる理由】
i-Staffは下記のような理由で多くのお客様にお選び頂いております。
1.全国から選ばれた採用率1%の優秀な人材が業務を対応
2.レスポンスが早くスピーディな業務対応
3.書類のスキャンなどオフライン業務も対応可
4.チーム制で対応する為退職リスクがない
業務をアウトソースする事でスマートな経営が可能になります。
ぜひこの機会にi-Staffの導入をご検討ください。