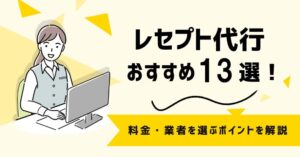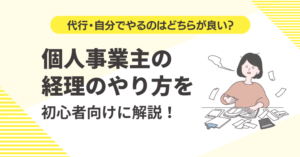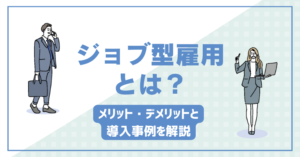業務委託のメリット・デメリットを企業側の目線で解説!正社員との違いや選び方のポイントを解説
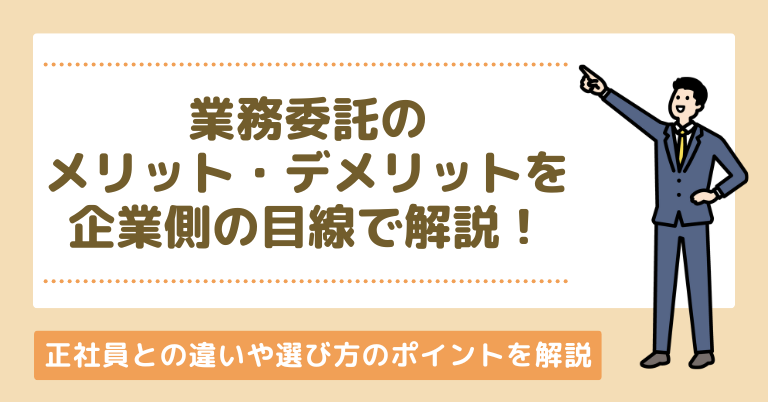
従業員のリソースを確保するためには、業務委託の活用がおすすめです。そこで、
「業務委託するメリットを具体的に知りたい」
「どの業務を委託すればいい?向いている業務が知りたい」
このようにお考えではありませんか。業務委託に向いていない業務もあるので、しっかり見極めなければ業務委託の恩恵を十分に受けられない恐れがあります。
そこで本記事では、下記をまとめました。
- 業務委託をするメリット・デメリット
- 業務委託を活用すべきケース
- 業務委託の注意点
現状の人材リソースに課題を感じている場合は、ぜひ最後までお読みください。
なお、業務委託をするならオンライン秘書・オンラインアシスタントサービス『i-STAFF』がおすすめです。i-STAFFは、幅広い業務に精通した優秀なスタッフが在籍しています。
i-STAFFの詳細は、下記よりご確認ください。
目次
業務委託とは?基本的な仕組みを解説

業務委託とは、企業が外部のフリーランスや事業者に業務を依頼する契約形態です。依頼側は受託側の労働力ではなく、仕事の成果や役務に対して報酬を支払います。
なお、民法上では「業務委託契約」という言葉は存在せず、下記の契約形態を総称して業務委託と呼んでいます。
- 請負契約:成果物の完成を約束する契約で、作業方法は受託側に任される形態
- 委任契約(準委任契約):業務の遂行自体を委託する契約で、成果の有無は問わない形態
業務委託では、依頼側は受託側に対して直接の命令ができません。また、受託側は労働時間や勤務場所について、原則として自由に決められます。
一方で、社会保険料の負担や労働基準法の適用もありません。企業側は必要な業務を必要な期間だけ外部に依頼できるため、柔軟な業務体制を構築できます。
業務委託と正社員の違い

正社員とは、企業と個人が雇用契約を結ぶ形態です。業務委託と正社員では、下記のような違いがあります。
| 項目 | 正社員 | 業務委託 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 企業と雇用関係がある | 対等な立場での契約関係 |
| 指揮命令 | 企業からの指揮命令を受ける | 企業からの指揮命令を受けない |
| 就業時間 | 企業が定めた時間での勤務 | 納期さえ守れば自由 |
| 報酬形態 | 給与として毎月支払う | 成果物に応じた報酬 |
| 福利厚生 | 社会保険や各種手当が適用 | 原則として対象外 |
業務委託において依頼側と受託側は対等な関係性であり、納品物の品質と納期が守られれば基本的に問題ありません。一方で、正社員は企業の指揮下に入るため、企業が定めた就業規則を守らなければなりません。
企業側にとっての業務委託のメリット3つ

業務委託を活用することで、企業側には3つのメリットがあります。
- コア業務に専念することで生産性向上を図れる
- 専門性の高い業務を依頼できる
- コスト削減による利益向上を見込める
システム開発やデザイン制作など専門的なスキルが必要になった場合、必要な期間だけ業務を依頼できます。ひとつずつ見ていきましょう。
コア業務に専念することで生産性向上を図れる
業務委託を活用すると自社の従業員がコア業務に専念でき、企業全体の生産性向上を図れます。担当者に時間的な余裕が生まれ、より質の高い仕事が可能です。
具体的な例を挙げると、記帳業務を委託した場合、経理担当者は日々の経理処理から解放されます。空いたリソースを使って、より付加価値の高い財務戦略の立案に時間を使えます。
売上に直接影響しないノンコア業務を外部に任せることで、自社の強みを活かせるコア業務により多くのリソースを投入可能です。結果として、企業全体の競争力強化につながり、持続的な成長を実現できます。
専門性の高い業務を依頼できる
業務委託のメリットとして、専門性の高い業務を必要なときだけ依頼できる点があります。たとえば、下記の業種です。
- システム開発
- デザイン
- 法務
- 税務
- 翻訳
- マーケティング
専門性の高い業務は、自社で人材を育成しようとすると時間がかかります。また、業務によっては、常に必要としているわけではありません。一方で、業務委託すると必要な期間だけピンポイントでプロに依頼できます。
たとえば、新規サービスの立ち上げ時だけマーケティングのプロに依頼したり、繁忙期だけデザイナーに業務を委託したりするなどです。即戦力となる人材が対応するため、より高い成果を期待できます。
コスト削減による利益向上を見込める
業務委託をすると、下記のようなコストを削減できます。
- 給与
- 福利厚生費
- 教育・研修費用
- オフィス・デスクなどの設備費用
正社員雇用の場合、これらのコストは毎月固定費として発生します。しかし、業務委託では、必要な期間に必要な分だけ契約することでコストの最適化が可能です。
また、業務委託の場合は委託費用のみを支払えばよいため、経理処理も簡素化できます。経理担当者の業務負担軽減にもつながり、間接コストの削減も可能です。結果として、企業の利益向上につながります。
企業側にとっての業務委託のデメリット

業務委託には企業側にとって、下記のようなデメリットがあります。
- 内容によってはコストが高くなる
- 自社にノウハウを蓄積しづらい
- スケジュールや品質の管理が難しい
業務委託では受託側に管理を任せるため、スケジュールや品質の把握が困難です。順番に紹介します。
内容によってはコストが高くなる
業務委託は、案件によっては正社員を雇用するよりもコストが高くなる場合もあります。特に、専門性が高い業務や緊急度の高い業務で、コストが増大しかねません。1時間あたりの報酬に換算すると、1時間数千〜数万円の報酬となることもあり得ます。
たとえば、システム開発やデザイン制作などの専門性の高い業務では、正社員の人件費を上回るケースがあります。また、緊急性の高い業務は、一般的に割増料金が加算されます。
業務委託を検討する際は、
- 業務内容
- 期間
- 必要な専門性のレベル
などを考慮し、正社員を雇用した場合とのコストを比較しましょう。特に、長期的な視点での費用対効果を見極める必要があります。
自社にノウハウを蓄積しづらい
業務委託をすると自社が関与しなくなるため、ノウハウが蓄積されにくいというデメリットがあります。委託先との契約が意図せず終了した場合、自社で業務を遂行するのが困難です。
たとえば、専門性の高い業務を委託している場合、業務の詳細な進め方やノウハウが委託先に依存してしまいます。そのため、将来的に自社で業務を内製化したい場合や、委託先を変更したい場合に支障をきたしかねません。
このような状況を回避するためには、委託業務の進捗状況や実施方法について定期的な報告会を設けたりマニュアル作成を依頼したりするなど、意識的にノウハウの共有を図る必要があります。また、自社の従業員を部分的に関与させることで、段階的にスキルやノウハウを獲得していくことも有効です。
スケジュールや品質の管理が難しい
業務委託は、自社の従業員と比べてスケジュールや品質の管理が難しいというデメリットがあります。労働時間は受託側の自由なため、品質や進捗状況について定期的な確認ができません。
進捗状況を把握するためには、定期的な進捗確認の機会を設けるのがおすすめです。また、品質を担保するためにはポートフォリオや過去の実績を確認し、最低限のレギュレーションをしっかりと定めておきましょう。
特に新規取引の場合は、小規模な業務から始めて徐々に範囲を広げていくといった段階的なアプローチを取るのも有効です。
業務委託を活用すべきケースとは?適した業務の特徴

業務委託を活用すべきケースを見極めることは、効率的な経営のために重要です。業務委託に適した業務を3つ紹介します。
- ノンコア業務
- 専門性の高い業務
- 繁閑の差が大きい業務
繁忙期と閑散期で業務量が大きく異なる場合は、業務委託が適しています。ひとつずつ見ていきましょう。
ノンコア業務
業務委託に適した業務のひとつが、ノンコア業務です。具体的な業務は、下記のとおりです。
- 経理・会計処理
- 給与計算
- データ入力
- 電話対応
- 資料作成
ノンコア業務は企業活動に必要不可欠ですが、売上に直接的な影響を与えるものではありません。そのため、業務委託による外部リソースの活用が有効です。
ノンコア業務を業務委託することで、自社の従業員は本来注力すべきコア業務に集中できます。また、専門業者に任せることで業務の質を担保しつつ、業務効率化の実現も可能です。
特に、定型的で反復的な業務は重要な判断を求められるケースが少ないため、業務委託に向いています。業務委託における最初の選択肢として検討してみましょう。
専門性の高い業務
自社の人材のみで対応できないほど専門性の高い業務は、業務委託がおすすめです。新しく人材を雇用してイチから教育すると、コストがかかります。また、専門性の高い人材を雇うと教育コストは抑えられますが、高額な給与を支払う必要があります。
業務委託であれば、すでに専門的なスキルを持った人材やチームに依頼可能です。また、最新のトレンドや技術に精通した専門家のノウハウを活用できるため、質の高い成果物を得られます。
プロジェクトの規模や期間に応じて柔軟に契約でき、効率的なリソース配分が可能です。
繁閑で量に差がある業務
繁忙期と閑散期で業務量に差がある業務は、業務委託での対応がおすすめです。
繁忙期に新しく人材を採用すると、閑散期では暇を持て余しかねません。1年を通してみたときに、必要以上の固定費がかかってしまいます。また、「仕事がない」という状況になりかねず、従業員のモチベーション低下も考えられます。
たとえば、季節性のある商品やサービスを取り扱っている場合、その季節にのみ業務委託で対応するのが有効です。問い合わせが増える場合は、コールセンターを業務委託すると最小限の負担で済みます。
このように、あらかじめ繁閑差がわかっている場合は、業務委託で乗り切るのがおすすめです。
業務委託の選び方!適切な契約先を見つけるポイント

業務委託を成功させるには、適切な契約先を選ぶことが重要です。下記のポイントに注目して、慎重に選定を進めていきましょう。
- 実績
- コミュニケーション力
- 費用対効果
業務委託は、業務の進捗や品質の管理を受託側に任せます。想定と異なる納品物にならないためにも、過去の実績を確認するのがおすすめです。順番に見ていきましょう。
実績
業務委託先を選ぶ際は、過去の実績を確認しましょう。受託側の実力がわからないまま依頼するのはリスクが高く、求める品質を満たさない納品物となる可能性があるからです。特に、同じジャンルでの実績を確認しましょう。
たとえば、経理業務を代行業者に委託する場合は、経理業務の実績があるかどうかを確認します。その際は、自社と同様の規模かどうか確認するのがおすすめです。
また、個人に依頼する場合はポートフォリオを確認しましょう。ポートフォリオがない場合は、テストとして仮契約するのもひとつの方法です。
実績もテストもなく契約するのはリスクが高いため、必ず確認しましょう。
コミュニケーション力
業務委託先を選ぶ際、相手のコミュニケーション力が重要なポイントです。コミュニケーションに不安や疑問が残る場合は、やり取りに時間を取られ、想定よりもリソースを確保できない恐れがあります。
下記のポイントをチェックして、相手のコミュニケーション力を見極めましょう。
- 要望に対する質問や提案の的確さ
- レスポンスの速さと丁寧さ
- トラブル発生時の対応力
- 報告・連絡・相談の頻度と質
契約する前のやり取りや面談を実施し、上記の内容を確認するのがおすすめです。受託側のコミュニケーションが上手な場合は、ストレスなく業務を遂行できます。
費用対効果
業務委託先を選ぶ際は、費用対効果を十分に検討しましょう。特に、専門性の高い業務は高額な場合が多いため、安さにばかり目が行きがちです。
しかし、費用の安さは質の悪さにつながるケースも多く、結果として安物買いの銭失いになりかねません。もちろん、費用が高ければいいというわけでもないため、見極めは困難です。
費用対効果を見極めるためには、まず自社で対応した場合の費用を算出します。
次に、業務委託先の候補に得られる成果を確認し、自社で対応した場合と比較しましょう。そのうえで、成果の高い業務委託先を選ぶのがおすすめです。
また、複数の業務委託先に問い合わせて、それぞれの見積もりを比較するのも重要です。
業務委託を導入する際の注意点

業務委託を導入する際は、下記のポイントに注意しましょう。
- 依頼する業務範囲と目的を明確化する
- 口約束ではなく契約書を交わす
スポット的な依頼だとしても、口約束ではなく契約書を交わすことを徹底しましょう。トラブルを避けるためには欠かせません。
依頼する業務範囲と目的を明確化する
業務委託を導入する際に重要なことは、依頼する業務範囲と目的の明確化です。曖昧にしたり受託側にしっかり共有しなかったりすると、修正回数の増加やトラブル発生につながりかねません。
明確化すべきおもなポイントは、下記のとおりです。
- 開始時期と終了時期
- 具体的な作業内容と品質基準
- 達成したい目標
依頼側と受託側の認識のズレを防ぐためにも、しっかりと明確化しておきましょう。特に、品質基準が明確化されていなければやり取りが増加し、自社での修正に時間がかかる恐れもあります。
結果として業務委託の恩恵がなくなりかねないため、最初に共有するのがおすすめです。
口約束ではなく契約書を交わす
業務委託では、口約束だけで業務を進めるのではなく、必ず契約書を交わしましょう。特に、個人と契約する場合に口約束で済ませるケースが見られます。
短期契約の場合が特に顕著で、「すぐに業務が終わるから」という理由が多いです。しかし、契約書を交わさない場合は、トラブルが発生したときに責任の所在を明確にできず口論になりかねません。
契約書の重要な部分は共通している場合も多いため、一度作成すれば使い回しが可能です。毎回イチから作る必要はないため、最初に作成してしまいましょう。
契約書を作成する際は、法務部門や顧問弁護士などの専門家に相談し、内容を精査するのがおすすめです。
メリット・デメリットを理解して業務委託を有効活用しよう

業務委託は、労働力ではなく仕事の成果に対して報酬を支払う契約形態です。リソースやコストを最適化するために有効ですが、闇雲に導入するのではなく、業務委託に適した業務を定めるのが重要です。
また、専門性の高い業務については、自社で対応するよりもコストがかかる場合もあります。メリットとデメリットをしっかりと把握し、自社に与える影響を見極めたうえで業務委託を活用しましょう。
オンラインで業務を
アウトソースするならi-Staff
こんな事でお困りでは御座いませんか?
・スタッフの雇用コストが高い・・
・雑務に追われてコア業務に集中が出来ない・・
・とにかく今すぐ業務を手伝って欲しい!
こんなお悩みがあれば、i-Staffで解決できるかも知れません!
【i-Staffが選ばれてる理由】
i-Staffは下記のような理由で多くのお客様にお選び頂いております。
1.全国から選ばれた採用率1%の優秀な人材が業務を対応
2.レスポンスが早くスピーディな業務対応
3.書類のスキャンなどオフライン業務も対応可
4.チーム制で対応する為退職リスクがない
業務をアウトソースする事でスマートな経営が可能になります。
ぜひこの機会にi-Staffの導入をご検討ください。